アナリティクスアソシエーション (a2i) > 活動報告 > セミナー >
活動報告
2016年3月11日金曜日、名古屋においてa2i名古屋「『優良顧客を獲得する』コンテンツマーケティング戦略!~ユーザーが思わず見たくなるコンテンツと行動分析~」(協力:株式会社アクアリング)が開催されました。
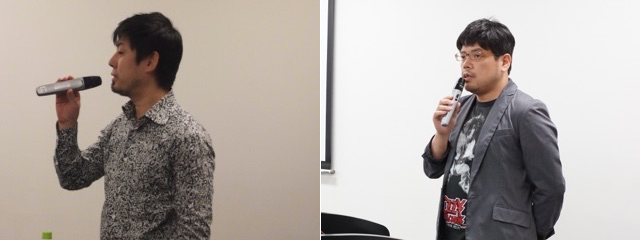
講師はSEOとコンテンツマーケティングの第一人者のお二人です。第一部は株式会社ウェブライダーの松尾 茂起 氏、第二部はガリバーなどでマーケティングに取り組んできた床尾 一法 氏、また第三部ではアクアリングの宮崎 篤武 氏をモデレーター役に、お二人のパネルディスカッションとQ&Aが実施されました。
松尾氏、床尾氏、お二人からはそれぞれのSEOやコンテンツマーケティングに対する考え方や取り組みについて、豊富な実例をまじえて、ご紹介されました。
第一部で、株式会社ウェブライダーの松尾 茂起氏からは、「ナースが教える仕事術」など、具体的な実績を中心にコンテンツマーケティングの取り組みが紹介されていきます。このコンテンツは運営から一年で、43記事を掲載、月間100万ページビューまでに成長しました。検索エンジンからの流入も87%と非常に多い状況です。基本的な姿勢は「検索ユーザー」とその検索エンジンを運営する「Google」が求めるコンテンツを発信しているからです。特に興味深かったのは、ユーザー目線のコンテンツ作りにあたって、「わかりやすさ」とは何なのか?「論理的」であるためにはどう考えればよいのか、と言った根本的な部分を、考えぬいていることです。また、その思考の結果を、例えば「見出しを使って文章のブロックを分ける」などかなり具体的な手法に落とし込んでいる点が、強く印象に残りました。

第二部では「ユーザー行動と文脈との対話」と題して、床尾 一法氏から長期のコンテンツ運用によるユーザーとの対話に重点をおいて、その考え方と取り組みが紹介されました。
コンテンツ作りを、ユーザーの気持ちに寄り添い対話し、価値ある体験をもたらすものと定義し、その対話のステージごとに見るべきデータも違ってきます。その中で、データの解析から取り組む人たちが、ユーザーの姿を理解することが大切です。長期的にはそれをチームの文化にできるか、という点が問われています。
その後、東証一部上場企業での具体的な取り組みをもとに、データ解析とそれに対するアクションにどう試行錯誤してきたか、得られたものが何か、という点が紹介されました。最後に、ツールや手法よりも、コンテンツ作りに取り組むための体制維持と仕組み作りの大切さが強調されました。
第三部はアクアリング宮崎氏がモデレーターとなり、お二人に質問をしながらパネルディスカッションを展開します。社内で取り組めない場合にどうしたらよいか? 更新の頻度はどのくらいかなどのトピックが取り上げられました。会場からも、SEO予算の説得の仕方など実際的な質問がよせられ、本音のQ&Aが展開されました。
アンケートには以下のようなコメントが寄せられました。
【女性 一般社員】 コンテンツを作成する時の心構えや意識することが分かった。
【男性 役員】 100万PVへのコツを直接教えていただきました。
【女性 その他】 漠然となんとなく理解していたことがすっきりと整理できました。ありがとうございました。
【女性 一般社員】 SEOやWEB、コンテンツなどを学びはじめたばかりですが、実際に行動ベースで明日から反映させることができる内容がたくさんあり、とても勉強になりました。
2025/07/16(水)
オンラインセミナー「【Canva入門 for マーケ担当者】広告・解析レポートをサクッと伝わるデザインにしてみよう!」|2025/7/16(水)
2025年スタートの新企画「ツール研究会」の第一弾は、「Canva」を取りあげます。 急なバナー作成やCTA差し込み、レポート用スライド作成 …
2025/06/26(木)
オンラインセミナー「サイトユーザーについて知りたいことをGA4で見る方法 ~アクセス解析の基本思考とレポート活用~」|2025/6/26(木)
このセミナーでは、「アクセス解析において持つべき視点」と、Google アナリティクス 4(GA4)の基礎を学びます。対象は初級者です。 企 …
2025/06/12(木)
【a2i交流会2025】デジタルマーケター大集合!a2i 5年ぶりの交流会|2025/6/12(木)
【追加分満員御礼】【5席追加】追加で5名の申込を受け付けます。定員になり次第受付終了いたします。(2025/6/9) 【満員御礼】増席を検討 …

【コラム】生成AIが変える買い物体験 「問いに答える積み重ね」が大事
アナリティクスアソシエーション 大内 範行本日のコラムは、ショッピングと生成AIについてです。 私たちは、果たして購買行動を生成AIで決めるようになるのでしょうか? 結論を先に言えば …

6月12日にa2iの交流会を開催し、多くの方とお話しする機会がありました。 また、5月30日にはWeb担当者Forum ミーティング 202 …

【コラム】生成AI浸透のカギは「組織のキャラクター」 アナグラム中島匠さんに聞きました
アナリティクスアソシエーション 大内 範行アナリティクスアソシエーションでは、不定期にインタビューを行っています。 第三回は、5月22日木曜日に行われた a2iのセミナー「生成AI活 …