アナリティクスアソシエーション (a2i) > 活動報告 > セミナー >
活動報告
2011年10月19日、アクセス解析のプログラム「ウェブアナリスト養成講座」第12回が行われました。講師は樽本徹也氏(利用品質ラボ代表)、内容は「ウェブのユーザ中心設計(UCD)とユーザテスト」です。
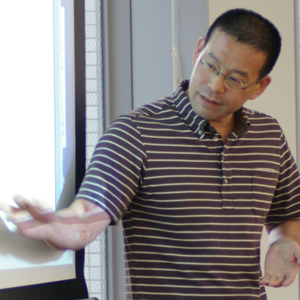 |
 |
 |
 |
◆第1部「UCD(ユーザー中心設計)とユーザテスト」
・ユーザーエクスペリエンスの基本的な考え方
ディズニーランド(ジェットコースターが売りではなく、ディズニーランドでは他の遊園地で同じ1日を過ごしても思い出の形が異なる)やスターバックスなど、その体験によって経済価値が異なる。
デザインにおいてはUIの構造(表層・骨格・構造・要件・戦略)の中でも特に戦略が共有できていなければ表層だけ付けても何の意味も無い。
・UCD(ユーザー中心設計)の四原則
1. ユーザーの声、聞くべからず → ユーザーの声とは体験をユーザ自身が自分で分析した結果である
2. みんなのためにデザインするのではなく、一人のためのデザインをする → ペルソナ。しかし架空と仮想は違う
3. 手を動かしながら考える → クリエイターはよく観察してみるとsketching〜prototypingを繰り返している、つまり手を動かしながら考えることが重要でこれを「デザイン思考」という。デザイナーでなくてもデザイン思考はできる。
4. 早期に失敗する → 失敗にはコツがある
・ユーザビリティ3要素
効果:タスクの完了
効率:最短距離で
満足度:不安、不満に思わせない
◆第2部「ユーザテスト実践テクニック」
・ユーザーテストをするにあたり必要な概念
総括的評価(測定が目的) → 英語で例えるとTOEIC
形成的評価(改善が目的) → 英語で例えるとNOVA
反証アプローチ → 現在のユーザーインターフェースはusableであると仮定してユーザーテストを実施し、徹底的に問題点を探す。問題点が見つかれば積極的に修正する。問題点が見つからなければ(反証できなければ)仮説は成立。リリース前はここまでもっていく(タスク完了率100%で製品をリリースすることはありえない)。
・5人のユーザで85%の問題が見つかる。
・実務の内容と進め方
実査前に行う内容の解説
インタビューガイドの実演
思考発話法によるユーザーテストのビデオ(資料用に実際の内容を再現して作成されたもの)の上映
スケジュール例・費用感・失敗パターン
◆簡易分析実習
ステップ1:どの画面で、何が問題なのか、問題点を書きだす。
ステップ2:各問題点のインパクトを判定。(深刻さを3段階で評価)
ステップ3:解決策を考える → 隣同士で解決策を話しあう
問題点とその評価及び1対1での解決策と総合的な解決策について分析例をご紹介
重要ポイント:
・解決策は必ずしも問題点に対して1対1とは限らない。真の解決策は”線”上にあるかもしれない=1個でいくつかの課題を解決できないか?
・テストの掟「勝手にテストしない」 → ユーザーテストをしないで作られたものは問題があって当たり前
講義が終わった後、質疑応答に並ばれる方が多かったのが印象的な講座でした。
2026/03/18(水)
オンラインセミナー「GA4×生成AIで改善提案の精度を高める ― AIから「使える施策」を引き出す実践アプローチ ―」|2026/3/18(水)
GA4によるサイト改善は、生成AIと組み合わせることで新しい段階に入りつつあります。 しかし一方で、「AIに分析させても表面的なコメントしか …
2026/02/19(木)
オンラインセミナー「GA4×ヒートマップで成果を出すCVR改善入門」|2026/2/19(木)
本セミナーは、Google アナリティクス 4(GA4)とヒートマップを活用してCVR改善の施策設計と効果検証を再現性高く行うための実践的な …
2026/01/22(木)
オンラインセミナー「検索行動・消費者分析ツール「DS.INSIGHT」の最新機能と活用事例」|2026/1/22(木)
ツール研究会の3回目は、DS.INSIGHTがテーマです。 このセミナーは、どなたでも参加可能です。 一般の方の申込には、ライト会員(登録・ …

【コラム】2026年以降も生き残るであろうアクセス解析業務とは?
株式会社MOLTS/株式会社月曜日のトラ 西 正広こんにちは、月曜日のトラの西です。 私は2006年に社会人となり、社会人1年目からアクセス解析ツールに触れてきました。2026年は、私がアク …

【コラム】生成AIはデータ分析をどう変えていくのか?自動運転レベルに学ぶ3段階の進化へ
アナリティクスアソシエーション 大内 範行2026年が明けました。今年は「生成AIを使ったデータ分析」が、大きなテーマになりそうです。 年初のコラムですし、まずは少し広い視野で、デー …

【コラム】生成AI時代 データ分析に必要な”料理人のスキル”は?
アナリティクスアソシエーション 大内 範行「生成AIでデータ分析は、どこまで簡単でおいしくなるのだろうか?」 今年最後のコラムです。来年に向けてそんなテーマを考えてみたいと思います。 …